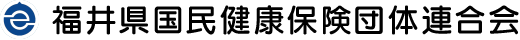基本理念
当連合会は、国民健康保険制度が国民皆保険体制の中核として地域住民の医療確保と健康の保持増進に資するという制度発足以来の目的を常に念頭に置いて、保険者の共同体としての責務を十分に認識し、信頼と安心を基盤とした良質の保険者サービスを提供します。
基本方針と主な事業
保険者を始め国保中央会、各県国保連合会等の関係団体と十分な連携を図りながら、次の4つの基本方針に基づいた事業を実施します。
基本方針1 精度の高い審査および確実な支払サービスの提供
精度の高い審査事務を行うため、各種研修等による職員の事務共助能力の向上による医療費の適正化を推進するとともに、近年増加傾向にある介護給付費については、県および保険者との連携を密にして適正化の推進に努めます。
基幹業務である診療報酬、介護給付費等の審査支払業務や、風しん対策事業および出産育児一時金の請求支払事業についても確実に行います。
I C T の活用による審査業務の強化と適正請求の推進
▪医療の高度化に伴いレセプトの内容が複雑化しているため、ICT技術を審査業務へ活用しつつ、高度な審査事務共助スキルを持つ職員の育成が必要となっています。審査委員等による医学的研修や職員間での算定ルールに関する知識・ノウハウの共有化の推進および、再審査の結果を分析し、審査事務へのフィードバックを月次サイクルで行っていくことで、職員育成と審査の質の維持を行います。
診療報酬審査における基準の統一に向けた対応の推進
▪「審査結果の不合理な差異の解消に向けた工程表」で示された審査基準統一の取り組みを引き続き積極的に推進するとともに、統一化された審査基準は確実かつ迅速に審査に反映させます。
介護給付費と障害者総合支援給付費における審査支払および介護給付適正化事業の円滑な実施
▪国が推進する、介護事業所等の生産性向上に向けたICT化を促すため、介護事業所等に対してケアプランデータ連携システムおよびインターネット請求の普及促進に取り組みます。
基本方針2 質の高い保険者サービスの提供
医療保険情報に係るデータ分析等に関する事業の推進を図るとともに、国や県の動向を注視しつつ、保険者のニーズを捉えたサービスを提供します。
レセプト・健診情報等を活用した分析事業等の推進
▪保険者が令和7年度以降に実施する「第3期データヘルス計画の評価・モニタリング」等に活用することができるよう、医療費や健診データ等の提供資料を検討します。
電算共同処理の効果的な運用
▪共同事業推進委員会に加えて、県が開催する各種会議や国保連合会支部が開催する会議への参加およびシステム操作研修会を通じて、保険者に共通する課題や要望を的確に把握し、既存事業の改善や新規事業の提案等に取り組みます。
▪国保連合会が提供している各種帳票やデータについて、県や保険者が利活用できるよう各種研修会を継続して実施します。
効果的な保健事業の実施に向けた保険者支援
▪「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業」において、保健事業支援・評価委員会などを開催し、国保ヘルスアップ事業実施保険者等への支援や、保険者におけるデータヘルス計画の効率的な保健事業展開のための支援を行います。
▪後期高齢者医療広域連合と連携し、保健事業支援・評価委員会等を活用して市町の実態に即した事業評価に協力することで、保険者の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の推進支援を行います。
▪特定健診等受診率向上や重症化予防事業など、保険者が取り組む保健事業を効率的・効果的に実施できるよう計画立案から評価までのプロセスに応じた支援を行います。
▪保健事業推進委員会や各種研修会等をとおして、保険者に共通する課題や要望を的確に把握し、既存事業の改善や新規事業の提案等に取り組みます。
第三者行為損害賠償求償事務の取り組みの強化
▪県と連携して保険者担当者を対象とした研修会を継続して開催することで、保険者による初動対応から請求に至るまでの事務の円滑化を支援します。
▪保険者が、保険者努力支援制度(市町村分) の評価指標にある第三者求償の取り組みについて、レセプトの抽出条件を見直し、保険者が効率的に被保険者への傷病届出勧奨が行えるよう支援します。
▪第三者行為による保険給付の早期発見と確実な請求のため、医療機関に対するレセプト特記事項記載の働きかけ、また、普及啓発グッズを用いた地域住民に対する制度周知も併せて行います。
基本方針3 保険者支援の基盤となるシステム整備と安定運用
保険者支援をはじめとする良質な保険者サービスの提供を実現するため、基盤となるシステムを整備し、安定運用を実現します。
各情報処理システムの安定的な稼働と継続的な効率化および適正化の推進
▪国保総合システムをはじめとする稼働中の各種情報処理システムについては、引き続き確実な運用と安定稼働に努めます。
▪各システムの運用サポートについては、実際の業務量に見合った委託料の定期的な見直しを継続し、経費の節減に努めます。
▪更改時期を迎える介護・障害者一拠点化システムおよび財務会計システムについては、円滑な移行と安定稼働を、課を横断した対応により実現します。なお、導入にあたっては入札による業者選定を行い経費の節減に努めます。
▪介護・障害者一拠点化システムの更改にあたっては、システム開発元である国保中央会と密な連携をはかりながら保険者の業務スケジュールを考慮した円滑なシステム移行に取り組みます。
情報セキュリティ対策の強化
▪ISMS認証を継続し、レセプトをはじめとする全ての情報資産を適切に管理するとともに、ISMSのプロセスを通じて情報セキュリティ対策の強化と改善を図ります。
▪各種セキュリティ研修を実施し、職員の情報セキュリティに対する意識の醸成と向上を図ります。
基本方針4 変化に対応できる組織と財政運営
当連合会を取り巻く状況の大きな変化に確実に対応するため、経営の透明性の向上、経営および経費分析の強化などに努め、持続可能な組織運営を図ります。
将来にわたり持続可能で安定的な財政運営
▪決算に基づく経営状況の分析と、複式簿記による財務諸表等を活用した財務管理を継続することにより、安定的な財政運営を図ります。
▪令和6年度に予定している介護・障害者一拠点化システムの更改等に備え、積立資産の計画的かつ適切な管理・運用を行います。
▪令和6年度に行う令和7年度から令和9年度にかかる手数料の見直しにおいては、将来にわたるICT関連経費の増加等の情勢を踏まえ、安定的経営ができるよう収支見込を精査した上でお示ししてまいります。
I C T の進展に対応できる人材の育成
▪統計分析の手法や分析結果の評価方法の知識の習得・技術の向上を図ることなどにより、当連合会が実施する事業の企画・立案に際して環境の変化や社会のニーズに対応できる人材の育成を図ります。
▪審査支払機関として、医療知識にかかる専門的な研修を通年で実施し、職員の審査事務能力の向上を図ります。
▪国保連合会・国保中央会以外の機関が開催する研修等に職員を積極的に参加させることにより、幅広い視野・知識を持った職員の育成を図ります。
▪職員の心身の不調を予防するため、法令に則った健康診断とストレスチェックを実施するとともに、それらの結果をもとに個別相談会を実施するなど、産業医と連携して職員の健康維持を図ります。
罹災などにおける事業停止期間の圧縮と迅速な事業復旧の強化
▪感染症の流行や予期せぬ大規模自然災害の発生に備え、システム面および組織運営の両側面から事業継続可能な仕組みづくりに取り組みます。